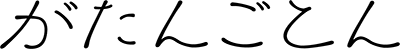-

穂村弘『短歌ください 双子でも片方は泣く夜もある篇』(文庫)
¥1,056
--- 歌人・穂村弘が読者の短歌を講評する人気シリーズ、文庫化第4弾が登場! 「双子でも片方は泣く夜もあるラッキーアイテムハンカチだった」……毎月変わるテーマごとに雑誌『ダ・ヴィンチ』読者から寄せられた短歌を、人気歌人の穂村弘が選び評する人気シリーズ第4弾! 今回は「転校生」「先生」「占い」「初恋」「曜日のある歌」「手紙」「ラブホテル」など全30テーマへの投稿作と、自由題作品から成る。解説は、かつて本連載の常連投稿者であり、現在は第一線の歌人として活躍する鈴木晴香。 (KADOKAWA)
-

『歌よみに与ふる書』正岡子規著・永井祐訳
¥2,420
SOLD OUT
--- 短歌史のマスターピースにして批評の名著、初の現代語訳! 120年以上前の燃えるようなテキストが今、現代短歌界のトップランナー永井祐によって再生される—— 正岡子規が1898年(明治31年)2月から10回にわたって新聞「日本」紙上に発表した伝説の歌論『歌よみに与ふる書』。俳句の近代化に力を注ぎ、文学者として影響力のあった子規が、つづけて短歌を近代化すべく論じた記事は、それまでの伝統的な和歌から現在まで続く近代短歌への転機となった。 初の現代語訳となる本書では、『歌よみに与ふる書』本編のほか、読者からの質問への回答「あきまろに答ふ」「人々に答ふ」、永井祐による正岡子規10首鑑賞、解説「子規と『歌よみに与ふる書』」を収録。 短歌ブームの現在、改めて短歌という詩型を考え直すきっかけとなる、タイムレスな魅力あふれる批評の書。 紀貫之は下手な歌人であって、『古今和歌集』はくだらないアンソロジーである。(「再び歌よみに与ふる書—『古今和歌集』について」) 前略。歌人のように馬鹿で気楽な人たちはまたとない。歌人たちの言うことを聞いていると、和歌ほどよいものはないといつも誇っているのだが、歌人たちは歌以外のことに無知なため歌が一番だとうぬぼれているだけなのだ。(「三たび歌よみに与ふる書—調について」) 噓を詠むのならまったくありえないこと、とてつもない噓を詠むべきである。そうでなければありのままに正直に詠むのがよいだろう。(「五たび歌よみに与ふる書—噓について」) なるほど、歌は青ざめて息を引き取ろうとする病人のようなものだろう。けれども私の考えはまったく異なる。和歌は精神こそ衰えたものの身体はまだ続いている。今、精神を入れ替えれば、ふたたび元気な和歌となって文壇を駆け巡ることができると保証する。(「七たび歌よみに与ふる書—言葉について」) 『歌よみに与ふる書』は伝説の書だ。しかし改めて読んでみると、なんだかやばい文章だった。実際に『歌よみに与ふる書』では前半から現状の和歌がほとんど全否定され、紀貫之をばっさりいったあとには柿本人麻呂の名歌も「半分いらない」ぐらいのことを言われる。わたしは二十年とか短歌を続けている人だけれど、そもそも人麻呂のこの歌のここがこういう風にダメだ、というようなことを言っている人をほとんど見たことがない。このような否定のかたまりみたいなテキストが次の時代を開いたということに改めて驚いてしまう。(永井祐「解説 子規と『歌よみに与ふる書』」より) (左右社)
-

穂村弘『短歌のガチャポン』
¥1,760
2022年刊行の一作目。 --- 穂村弘が選ぶ何でもありの短歌ガチャ100 現代短歌のフロントランナー穂村弘が腕によりをかけて選んだ、明治から現在までの短歌100首。うつくしい短歌、不思議な短歌、へんな短歌、おかしな短歌、不気味な短歌、かなしい短歌……。好きなところからひとつずつ取り出して、なんでもありのマジカルな短歌ワールドをとことん楽しもう。最初は意味のわからない短歌も、穂村弘の切れ味のいい鑑賞文を読めば納得できるはず。穂村弘は言う。「ガチャポンのハンドルをガチャガチャ回すと、カプセルに入った何かがポンと出てきます。ジャンルだけは決まってて、でも、その中の何が出るかはわからない。だから、わくわくして夢中になりました。」短歌の楽しさと多様性を、ミステリアスでファンタスティックなメリンダ・パイノのカラーイラスト25点と共に詰め込んだ、ホムラ印のガチャポン・マシーンがここに。 (小学館)
-

穂村 弘『短歌のガチャポン、もう一回』
¥1,870
--- 明治から令和まで、新たな100首が登場! 「バスの中で、或いは珈琲を飲みながら、或いはトイレに起きた明け方に、誰かの短歌を思い出すことがある」(「あとがき」より)。 現代短歌のトップランナー・穂村弘がふと思い出して嬉しくなったり、たまたま目に飛び込んできて「いいな」と思った100の短歌を集めた一冊。話題の前作『短歌のガチャポン』から時を経て、明治から令和までのきらめく100首が新たに登場! 例えば……。 乱気流に突入します、すみません機長は乱気流が好きなので(ぬぬ) 大河に投げんとしたるその石を二度みられずとよくみいる心(中原中也) 枕木の数ほどの日を生きてきて愛する人に出会はぬ不思議(大村陽子) 男性は土俵に入ってよい しかし土俵の外に出てはならない(田村囲) 友達の遺品のメガネに付いていた指紋を癖で拭いてしまった(岡野大嗣) 前作に続きメリンダ・パイノ氏による作品世界を広げるキュートなカラーイラスト25点も収録。 ページをめくるたびに、ガチャポンを回す時のような「わくわく」を感じられる一冊です! (小学館)
-

北海学園短歌会誌『華と硝烟』各号
¥1,000
北海学園大学短歌会誌『華と硝烟』、遂に刊行! 北海学園の初代文学研究科長であった、「菱川善夫の業績を受け継ぎ、おのおのの短歌研究賞史を練ることを目標とする」同会から、年一冊刊行されていきます。(また、編集部は同大学の田中綾研究室に置かれています。) <【創刊号】内容紹介> 会員の作品に加え、OBの石井僚一さんの作品も掲載されています。 特筆すべきは、近代短歌研究への特化だと思います。書評も、現代と、明治・大正・昭和、と分けられて掲載されています。 また、評論も厚く、口語短歌運動において重要とされる「清水信ノート」(山田航)の、新技巧派批判、新律格、新短歌の動向など、とても興味深いです! 渡辺駆さんの評論「戦争の正身(むざね)」では短歌史の意義を近代天皇制、軍国主義などを通して分析し、どう短歌に関わるべきかを論じています。 また、1940年の合同歌集『新風十人』を通して、篠弘の視点と比較しながらの、菱川善夫論も掲載。 峰艷二郎さんの評論では、フェミニズムやジェンダー理論からの批判を取り上げながら、菱川善夫の女歌論について、そこから山中智恵子の両性具有性への論について展開されていきます。 濃厚で紹介し切れませんが、表紙の書からも漂う芳しさ…!皆さんの短歌作品も素敵で、今後の会の発展が楽しみです! 是非とも、実物で味わって戴ければと思います〜!(よ) <【第2号】内容紹介> 招待作品は岡本真帆さん。 岡本真帆歌集に呼応した石井僚一さんの新作。 山田航さんは評論(総合誌向きのキャッチーな内容)&新作も発表されています。
-

『第三回 あたらしい歌集選考会の記録』
¥1,100
--- 三回目の開催となる公募企画「第二回 あたらしい歌集選考会」の結果を収録しました。 選考会の結果報告となる本書では、選出された2名の歌人による各100首の短歌と、それぞれの選者である、木下龍也と岡野大嗣による選出理由を収録しました。選考会の記録として作成した簡素なものですが、掲載作品の力とそれを推しだす熱に溢れた一冊です。 『第三回 あたらしい歌集選考会の記録』 目次 ・篠原仮眠 100首(岡野大嗣 選出) ・丸太洋渡100首(木下龍也 選出) ・選出理由(木下龍也、岡野大嗣) 仕様:A5サイズ、中綴じ 頁数:64頁 (ナナロク社)
-

『AIは短歌をどう詠むか』
¥1,034
--- 短歌AIを開発しながら考えた、人間だけにできること、AIにしかできないこと。 「型」と「らしさ」を身につけるには? AIが学んでいく姿から、短歌の面白さも見えてくる! 令和の世で、空前のブームとなっている「短歌」。 そしてもはや私たちの日常にも深く入り込んでいる「AI」。 感情を持っていないはずのAIが、 どうやって、まるで人のように短歌を詠めるようになるのか? そこで見えてきたAIと人との幸福な関係性とは? <短歌AI>の開発に心血を注いできた、気鋭の研究者がわかりやすく解説します。 短歌とAI、いずれもへの扉を開いてくれる本! (講談社)
-

永田和宏『現代秀歌』
¥1,122
--- 佐藤佐太郎から塚本邦雄、穂村弘へ──「今後百年読まれ続けて欲しい」、主として戦後の秀歌百首を編む。 大好評を得た『近代秀歌』の続篇として、「今後100年読まれ続けて欲しい」、主として戦後の秀歌100首を編む。佐藤佐太郎や近藤芳美から、塚本邦雄、寺山修司、岡井隆、そして俵万智から穂村弘へ。大きな変化を経た時代に、歌人たちは何を感じ、何を試みてきたか? 著者ならではの視座から、歌の現在を、そして未来を語る一冊。 (岩波書店)
-

塚本邦雄『新版 百珠百華─葛原妙子の宇宙』
¥2,750
--- 新仮名遣いで読みやすくなった 塚本ワールドに最適な一冊 皆川博子さん激賞! 塚本邦雄に導かれ葛原妙子の宇宙を逍遙する これにまさる贅沢があらうか 深い教養の泉から湧き出づる叡智を養ひとした大輪の花々は洞察の力を芯に秘める 【著者プロフィール】 塚本邦雄(つかもと・くにお) 歌人。1951年に第1歌集『水葬物語』を刊行、岡井隆、寺山修司らと前衛短歌運動を展開。詩歌文学館賞、迢空賞など多数受賞。2005年没。 (書肆侃侃房)
-

川野芽生『幻象録』
¥1,980
泥文庫003 雑誌『現代短歌』で連載されていた「幻象録」。その前身の「歌壇時評」とともに、2019年から2023年までの5年近くにわたる連載を書籍化。 きれっきれに、時代と短歌を評論しています。 --- わたしの文章に美質があるとすれば、感情と論理が切り離されていないところだろうと思う。(略)わたしは感情を殺すことなく、むしろ研ぎ澄ませて外界と相対し、心が知らせたことを論理的に整理し、分析して、他者と共有可能なかたちにしようとしてきた。わたしはずっと怒っていて、同時に、その怒りを開かれた場に置こうとしていた。そうなのだと思う。 (「あとがき」より) (泥文庫)
-

江田浩司『短歌にとって友情とは何か』
¥1,980
--- 歌人の友情はいかにして可能か? 友情を妨げる歌壇の力学とは? 問われたことのない問いから、歌人の精神のありようが見えてくる。 <本書の内容> Ⅰ 短歌にとって友情とは何か 序章 「ずっと、ここにいるから。」 1 友情の限界 ―石川啄木と金田一京助 2 友情の本質 ―与謝野鉄幹と北村透谷・薄田泣菫/石川啄木と土岐善麿 3 孤独と友情 ―斎藤茂吉と吉井勇 4 友情の美点 ―玉城徹と級友/岡井隆と相良宏 5 友情は愛に似て ―与謝野晶子と山川登美子/三ヶ島葭子と原阿佐緒 6 友情と恋愛の間に ―田辺元と野上弥生子/西行と西住 7 友情を包む光 ―岡井隆と米田利昭 8 友情と夭折 ―小中英之と小野茂樹 9 友情と追悼 ―岡井隆と大岡信 10 友情と思想 ―馬場あき子と中国革命 11 時代を超える友情 ―本歌取り 12 友情の消滅 ―二冊の本 13 批評の不在 ―友情を妨げる力学について 14 超実践的短歌鑑賞用語辞典 終章 「また、あいましょう。」 Ⅱ 寺山修司をめぐる断想 1 不連続体について ―未発表歌集『月蝕書簡』を読む 2 「新しい個」の表現 ―『寺山修司の俳句入門』を読む 3 寺山修司と「作者の死」 (現代短歌社)
-

『あとがきはまだ 俵万智選歌集』
¥1,980
SOLD OUT
--- 『サラダ記念日』から最新作『アボカドの種』まで。 俵万智自身が、書評家・渡辺祐真(スケザネ)と選んだ220首。オリジナル歌集へのガイドになる80ページ超のスケザネ「全歌集の鑑賞の手引き」付。 著・俵万智 編・渡辺祐真/スケザネ 俵さんの短歌が、時を超えて、いまあなたの心を摑みます。 *全七歌集に加えて、現在入手困難の企画歌集『とれたての短歌です。』『もうひとつの恋』からもセレクト。俵万智さんの「選歌集」では唯一流通している本となります。 ◎おもな収録歌 今日までに私がついた噓なんてどうでもいいよというような海 ──『サラダ記念日』 まだ何も書かれていない予定表なんでも書けるこれから書ける ──『とれたての短歌です。』 デジタルの時計を0、0、0にして違う恋がしたい でも君と ──『もうひとつの恋』 百枚の手紙を君に書きたくて書けずに終わりかけている夏 ──『かぜのてのひら』 優等生と呼ばれて長き年月をかっとばしたき一球がくる ──『チョコレート革命』 みかん一つに言葉こんなにあふれおり かわ・たね・あまい・しる・いいにおい ──『プーさんの鼻』 振り向かぬ子を見送れり振り向いたときに振る手を用意しながら ──『オレがマリオ』 別れ来し男たちとの人生の「もし」どれもよし我が「ラ・ラ・ランド」 ──『未来のサイズ』 人生は長いひとつの連作であとがきはまだ書かないでおく ──『アボカドの種』 下記、俵万智「まえがき」より引用 長く歌をつくっていると歌集も増え「どれから読めばいいですか?」と聞かれたりする。スケザネさんという素敵な読み手を得て、選歌集を編めることは、ありがたい機会だ。まず彼が短歌を選び、そのセレクトを尊重しつつ、どうしても私が入れたい歌を加えてもらった。歌集ごとの鑑賞や位置づけも丁寧にしていただいたが「こう読め」というよりは「こんなふうに自由に読んでいいんだ」と受けとめてほしい。そして気に入った歌集があれば、ぜひ手に取ってまるごと読んでいただけたらと思う。そこから先は、あなたセレクト、あなたの鑑賞の世界が広がるはずだから。 著者プロフィール ♦俵 万智 (たわら・まち) 1962年大阪府生まれ、早稲田大学第一文学部卒。86年、「八月の朝」五十首で第32回角川短歌賞を受賞。 87年、第一歌集『サラダ記念日』を刊行。 同歌集で第32回現代歌人協会賞受賞。96年より読売歌壇選者。2006年、第四歌集『プーさんの鼻』で第11回若山牧水賞、第六歌集『未来のサイズ』で第55回迢空賞、第36回詩歌文学館賞受賞。評論では『愛する源氏物語』で第14回紫式部文学賞、『牧水の恋』で第29回宮日出版文化賞特別大賞。 宮崎で毎年開催される高校生の「牧水・短歌甲子園」審査員を務め、2020年には歌舞伎町ホストたちの歌集『ホスト万葉集』『ホスト万葉集 ・巻の二』や、アイドルが短歌に挑戦する「アイドル歌会」に、企画当初から選者として関わった。現代短歌の魅力を伝え、すそ野を広げた創作活動により2021年度朝日賞を受賞。最新歌集『アボカドの種』を2023年十月刊。2023年11月、紫綬褒章受章。 ♧渡辺祐真(わたなべ・すけざね) 1992年東京都生まれ。作家・書評家。書評系YouTuberとして活動をはじめ、自身のチャンネル「スケザネ図書館」で、書評や書店の探訪、ゲストとの対談など多数の動画を展開し注目を集める(俵万智出演回は2021年7月6日配信 https://www.youtube.com/watch?v=TR-6-rt7_Pk&t=279s )。2022年4月から毎日新聞文芸時評担当。TBSラジオ「こねくと」レギュラー、TBSポッドキャスト「宮田愛萌と渡辺祐真のぷくぷくラジオ」パーソナリティー(2024年3月現在)。著書に『物語のカギ』、共著に『吉田健一に就て』『左川ちか モダニズム詩の明星』など。最新の編著に『みんなで読む源氏物語』がある。 (短歌研究社)
-

高野公彦『短歌練習帳』
¥1,870
SOLD OUT
--- 実作者必携の入門・指南書!練習問題形式で、例歌に則し、多角的にアプローチしながら短歌の本質に迫る24章。 (本阿弥書店)
-

島田修三『古歌そぞろ歩き』
¥3,080
--- 記紀万葉から近世短歌まで著者の和歌への造詣が溢れんばかりの注目の一書。「歌壇」連載待望の単行本化。 (本阿弥書店)
-

高野公彦・栗木京子『ぼくの細道うたの道』
¥3,300
--- 歌人・高野公彦の水脈をたどるインタビュー集。インタビュアー・栗木京子。 (本阿弥書店)
-

今野寿美『歌ことば100』
¥2,970
--- 現代短歌にも脈々と息づく古くからの「歌ことば」を豊富な例歌と該博な知識で一語一語読み解く。「歌壇」好評連載待望の単行本化。 (本阿弥書店)
-

『おやすみ短歌』枡野 浩一/pha/佐藤 文香
¥2,750
SOLD OUT
phaさん特製の『猫リング栞』付きです! --- 人気歌人・作家・俳人がコラボし、安眠がテーマの短歌を百首集め、見開きで紹介する現代版「百人一首」。 短い文章付きなので、短歌の読み方がわからなくても楽しめます。 この本のページをパラパラとめくるうち、ここちよい眠りの世界に誘われることでしょう。 百首を紹介!(掲載順、敬称略) 橋爪志保/佐伯紺/初谷むい/水野葵以/加藤治郎/正岡豊/谷川由里子/宇都宮敦/柳澤真実/木下侑介/工藤吉生/土岐友浩/井上法子/鈴木加成太/岡本真帆/山階基/夜夜中さりとて/佐々木朔/大室ゆらぎ/俵万智/花山周子/柴田有理/上本彩加/遠藤健人/三田三郎/辰巳泰子/藪内亮輔/魚村晋太郎/大森静佳/光森裕樹/仲田有里/伊舎堂仁/永田和宏/岡野大嗣/村上きわみ/小島ゆかり/青松輝/多賀盛剛/?田恭大/平出奔/望月裕二郎/絹川柊佳/鈴木ちはね/吉岡太朗/東直子/toron*/斉藤真伸/上坂あゆ美/田丸まひる/田村穂隆/早坂類/石川美南/丸田洋渡/伊勢谷小枝子/山下翔/山田航/小島なお/山中千瀬/門脇篤史/佐藤弓生/本多真弓/三上春海/竹中優子/笹公人/千種創一/北山あさひ/堂園昌彦/川野芽生/阿波野巧也/笹井宏之/佐々木あらら/天野慶/笠木拓/帷子つらね/永井亘/平岡直子/瀬口真司/千葉聡/干場しおり/石井僚一/佐藤りえ/枡野浩一/我妻俊樹/伊藤紺/はだし/永井祐/穂村弘/渡辺松男/岡崎裕美子/荻原裕幸/濱田友郎/佐原キオ/楠誓英/笹川諒/五島諭/雪舟えま/木下龍也/上篠翔/仁尾智/陣崎草子 (実生社)
-

尾崎まゆみ『レダの靴を履いて 塚本邦雄の歌と歩く』
¥2,200
北山あさひ『ヒューマン・ライツ』刊行記念選書フェア「心に火を灯す13冊」 塚本邦雄の歌に高いハードルを感じていたわたし。尾崎さんの解説は塚本の歌を覆う「難しそうな感じ」を丁寧にほどいて、そっと目の前に差し出してくれます。短歌初心者にもおすすめ! (北山あさひ・コメント) --- 八〇年代後半、若くして塚本邦雄に出逢ってしまった著者は、塚本ワールドの虜になり、塚本が語る短歌と言葉の世界に引き込まれていく。塚本亡き後、訪れた日本現代詩歌文学館で、偶然、塚本の遺品に遭遇した著者に、あの醸成された至福の時間が還ってくる。そしてふたたび、塚本の短歌とともにあるき始める。 二〇二〇年、塚本邦雄は生誕百年を迎える。 (書肆侃侃房)
-

『女のかたち・歌のかたち』
¥1,650
−−− 女性の歌をテーマ別に集め、短歌を作らない一般の読者も気楽に読めるように解説を付けた一冊。 「西日本新聞」に約半年にわたり、連載された。 短歌史上初、与謝野晶子の出産の歌。 20歳で離婚、幽閉の身となっていた柳原白蓮が思いを綴った手紙。 昭和29年、その後の女性の歌の噴出口となった中城ふみ子の登場。 その他、著者と同時代を生きた道浦母都子、河野裕子、永井陽子等、60人以上の女性歌人が取り上げられており、 読者は20世紀100年の女性の嘆きやよろこびを追体験することが出来る。 現代短歌における女性の歌を追求し続けている阿木津英による最新評論集。 (短歌研究社)
-

東直子『現代短歌版百人一首 花々は色あせるのね』
¥1,870
−−− 歌人・東直子が、今の言葉で百人一首をすべて詠み直し、より身近に感じられるようになりました! 自身によるカバー・本文イラスト、作品解説付き。 ◎花々は色あせるのね長い雨ながめて時は過ぎゆくばかり (花の色はうつりにけりないたづらに我が身世にふるながめせしまに 小野小町) ◎マイホームは都心の東南いい感じ憂鬱山と人は言うけど (わが庵は都のたつみしかぞ住む世をうぢ山と人はいふなり 喜撰法師) ◎死んでもいいと思ってたけど君のために長く生きたい一緒にいたい (君がため惜しからざりし命さへ長くもがなと思ひけるかな 藤原義孝) ◎一夜君が鳥の鳴きまねしてきても逢坂の関越えさせません (夜をこめて鳥のそら音ははかるともよに逢坂の関はゆるさじ 清少納言) 百人一首を一気読みすると、そこに確かな時代の流れがあり、人間関係のう ねりがあることに気づく。のどかな景色から始まり、恋のかけひきなどで生じ た恨み辛み悲しみが蠢く一方、愛を喜び、動植物を愛で、景色の美しさに感嘆 する。遠い遠い昔の和歌の中の人の心が、生々しく胸に浮かび上がってくる。 交響曲のようにそれらが響き合う醍醐味に、深く感動した。小倉百人一首を編 纂したとされる藤原定家の手腕にしみじみと感じ入る。 (あとがきより) (春陽堂書店)
-

『『女人短歌』 小さなるものの芽生えを、女性から奪うことなかれ』
¥2,420
--- わたしたちの短歌誌をつくろう! 女性のために女性自身の手によって編まれた歌誌『女人短歌』。第二次大戦の敗戦直後に創刊され、48年にわたって刊行された。 男性中心の歌壇のなかで結社を超えて女性たちが結束し、相互研鑽に努めた。女性歌人が活躍できる地平を切り拓いた功績は大きい。 五島美代子、長沢美津、生方たつゑ、阿部静枝、山田あき、葛原妙子、中城ふみ子、森岡貞香ら、『女人短歌』に集った歌人たちの熱き魂のリレーを追う。 歌誌『女人短歌』について初めての総合的研究書。 (書肆侃侃房)
-

穂村弘『短歌ください 明日でイエスは2010才篇』(文庫)
¥748
--- 人気歌人・穂村弘が、読者の短歌を講評。実践的短歌入門 人気歌人・穂村弘が選を務める短歌投稿コーナー(本の情報誌『ダ・ヴィンチ』連載)の書籍化第2弾が待望の文庫化。鮮やかな講評が、短歌それぞれの魅力をさらに際立たせる。 (講談社)
-

【サイン本あり】歌集副読本『老人ホームで死ぬほどモテたい』と『水上バス浅草行き』を読む
¥1,320
SOLD OUT
--- 「歌集副読本」とは歌集を味わい尽くすための助けとなる読みものです。 2つの出版社(ナナロク社と書肆侃侃房)の2022年の話題の歌集2冊の著者が、互いの歌集の魅力について、愛情こめて書き合いました。 ◎プロフィール 上坂あゆ美(うえさか・あゆみ) 1991年、静岡県生まれ。2017年から短歌をつくり始める。2022年2月に第一歌集『老人ホームで死ぬほどモテたい』を書肆侃侃房から刊行。 岡本真帆(おかもと・まほ) 1989年生まれ。高知県、四万十川のほとりで育つ。未来短歌会「陸から海へ」出身。2022年3月に第一歌集『水上バス浅草行き』をナナロク社から刊行。 (ナナロク社)
-

穂村弘『短歌ください 海の家でオセロ篇』
¥1,980
--- 歌人・穂村弘が短歌を選び、講評する。あなたもきっと詠んでみたくなる 歌人・穂村弘が、読者の短歌を選んで講評。本の情報誌『ダ・ヴィンチ』の人気連載、書籍化第5弾。短歌を詠む人も、読む人も。言葉のワンダーの世界へいざなう、実践的短歌入門。
書肆侃侃房「新鋭短歌シリーズ」一挙アップ!