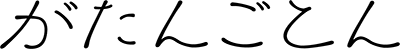-

【サイン入り】『放課後によむ詩集』
¥1,980
編者、小池昌代さんのサイン入り。 小池さんの書き下ろし詩が掲載されたフリーペーパーも同封します。 --- 仲間から離れ、一人になった時間に、ゆっくりと向きあえる、31の詩を選びました。それぞれの詩の後に付された小池昌代さんの言葉は、読者に寄りそい、詩の世界に風を通します。すべての人の「放課後」に贈るアンソロジー。 ■ 古今東西から31 の詩を精選して掲載 ■ 読みを広げ、助ける、詩人によるコメント ■ 巻末「詩人紹介&ブックガイド」が充実 (理論社)
-

三枝昂之『夏は来ぬ』
¥1,980
--- ながらく品切れになっていた三枝昂之さんの著書『夏は来ぬ』が文庫版となって再登場しました。 静岡新聞に三年半にわたって連載された、詩歌の鑑賞です。古典からレミオロメンの歌詞まで、季節に合った詞が取り上げられています。 ※青磁社Twitterより引用 (出版社︰青磁社)
-

斉藤倫『ポエトリー・ドッグス』
¥1,760
--- 「このバーでは、詩を、お出ししているのです」 今夜も、いぬのマスターのおまかせで。詩人・斉藤倫がおくる、詩といまを生きる本。 『ぼくがゆびをぱちんとならして、きみがおとなになるまえの詩集』につづく、31篇の詩をめぐるストーリー。 「詩っていうのは、おもい出させようと、してくれてるのかもね。このじぶんだけが、じぶんじゃなかったかもしれないことを。このせかいだけが、せかいじゃなかったかもしれないことを」 T・S・エリオット 吉岡 実 ガートルード・スタイン アメリカ・インディアンの口承詩 萩原朔太郎 ボードレール 杉本真維子 宮沢賢治 石原吉郎 ウォレス・スティーヴンズ 石牟礼道子 アルチュール・ランボー ……ほか全31篇の詩をめぐる物語
-

茨木のり子『詩のこころを読む』
¥990
詩人・茨木のり子さんが、自身の“たからもの”である様々な名詩を、愛情たっぷりに紹介しています。 代表作である「自分の感受性くらい」などの詩から、“強い女性”というイメージが大きかった茨木さんですが、本書の文章はとてもあたたかく包容力があり、詩や詩人に対する敬愛の念が伝わってきます。著者の印象が変わるとともに、ますます大好きになってしまいました。 1979年に刊行されてから何度も版を重ね、約半世紀にも渡って読み継がれている名著です。 --- いい詩とは,ひとの心を解き放つ力をそなえているばかりか,生きとし生けるものへのいとおしみの感情をも誘いだしてくれます.詩人である著者が,その心を豊かにしてきた詩の宝箱の中から忘れがたい詩の数々を選びだし,情熱をこめて語ります.ことばの花々にふれてみなさんは,きっと詩の魅力にとらえられるでしょう. 【著者プロフィール】 茨木のり子(いばらぎ のりこ) 1926-2006年.1946年東邦大学薬学部卒業.敗戦後の新しい息吹きにつき動かされ,1950年頃から詩作をはじめる.詩誌『詩学』に投稿し,同誌新人特集号に掲載.1953年川崎洋氏と2人で,同人詩誌『櫂』を発刊.詩集『対話』『見えない配達夫』『鎮魂歌』『人名詩集』『自分の感受性くらい』,エッセイ集『言の葉さやげ』,詩人の伝記『うたの心に生きた人々』などがある.
-

岡井隆『岡井隆の忘れもの』
¥3,300
--- 斎藤茂吉、森鷗外、正岡子規、与謝野鉄幹・晶子、 種田山頭火、ベンヤミン、多和田葉子、 穂村弘、高橋睦郎、大岡信、北川透、 石原吉郎、荒川洋治、平出隆、蜂飼耳……などの人々に言及。 時代の表現者たちを自在に、 時にやさしく、時に鋭く読み解いていく。 岡井隆の忘れものは、岡井隆の遺言であり、 日本語の美しさへのあらゆる賛美である。 詩の美しさを支えるのは、詩の背後の時代でもあるのだ。 いい詩を、まことにいい詩として解読できたとすれば、その時代がわかったともいえるのである。 ―岡井 隆 【章立て】 暗黒救済のメッセージ/美しき時代の詩歌/孤心とうたげ/詩歌句の未来/詩における物語性/啄木の方法 /対談 岡井隆『暮れてゆくバッハ』を読む/人生の贈りもの コラム6点も収録 【著者プロフィール】 岡井 隆(おかい・たかし) 1928年名古屋市生まれ。慶應義塾大学医学部卒。内科医。医学博士。1945年17歳で短歌を始める。翌1946年 「アララギ」入会。1951年現在編集・発行人をつとめる歌誌「未来」創刊に加わり、逝去直前まで編集・発行人をつとめる。1983年歌集『禁忌と好色』により迢空賞受賞。2010年 詩集『注解する者』により高見順賞を受賞。2015年『暮れてゆくバッハ』(書肆侃侃房)。『『赤光』の生誕』など評論集多数。日本藝術院会員。2020年7月10日心不全のため死去。享年92歳。2022年に遺歌集『阿婆世』(砂子屋書房)が刊行される。 (書肆侃侃房)
-

日本の詩×世界の詩 て、わたし(5〜7号)
¥1,320
日本の詩×世界の詩 「て、わたし」販売始まりました! 「たったいま、世界で書かれている言葉に日本語で触れられる機会は多くありません。日本で書かれている言葉がどんな位置にあるのかを知る機会もほとんどありません」という思いから、世界の詩の翻訳と日本の書き手を同時に収める素敵な本です。 ーー 第5号「ことばから根をはる私」 特別ゲストを含め七人の詩人の作品を取り上げています。 日本人の書き手では中原中也賞・鮎川信夫賞を受賞された暁方ミセイさん、Yale大学卒業で日米の現代詩に通じた佐峰存さん、デビュー以来全ての詩集で賞を受賞されている渡辺めぐみさん。 海外の書き手は、トランスジェンダー女性としての生きづらさをテーマに詩を書くJ・ジェニファー・エスピノザ(USA)、2019年に発行予定の詩集「Deaf Republic」が発行前からピューリッツァー賞候補の呼び名の高いウクライナ系アメリカ人の詩人イリヤ・カミンスキー。南米で初めてフェミニズム詩を書き、2018年5月23日に南米のGoogleのトップ画像を飾ったアルフォンシーナ・ストルニを紹介しています。 また、BRUTUSで「札幌の正解」特集でも取り上げられた歌人の山田航さんをお迎えし、短歌を通じた文芸批評の可能性に挑戦します。 ーー 第6号では「生きづらさを越(超)えて生きる」をテーマにして、6人の詩人を紹介。 ・成宮アイコ x ローリステリー・ペーニャ・ソラーノ(訳:大崎清夏) ・荒木田慧 x 余秀華(訳:小笠原淳) ・鳥居 x クリストファー・ソト(訳:山口勲) 新たなチャレンジとして宮尾節子さんの連載、詩との出会いをさまざまな方に教えていただくシリーズ「Close Encounters of Poetry」を開始。 装画には川崎継子さんが初参加。コラージュで新たな装いを加えています。 ーー 第7号は「フラニー・チョイ:導くための言葉」。 韓国系のアメリカ合衆国の女性詩人 フラニー・チョイさんの作品を紹介するとともに、彼女の言葉と行き交う、日本語の書き手(堀田季何さん・西山敦子さん・ヤリタミサコさん)を紹介しています。 新詩集「女に聞け」を刊行したばかりの宮尾節子さんの連載詩、そして詩と人との出会いを紹介するコーナー・Close Encounters of Poetryでは中村仁美さんによるアイルランドのポエトリーシーンを紹介。 (※公式サイトの紹介文より一部抜粋・編集して掲載)
書肆侃侃房「新鋭短歌シリーズ」一挙アップ!