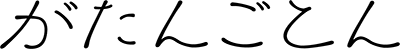-

尹 雄大『「要するに」って言わないで 本当の自分の思いに気づくとラクになる』
¥1,980
SOLD OUT
--- ★東畑開人さん(臨床心理士) 「尹さんは体の声をきき、通訳してくれる。生き延びるために学んだ方法だ。」 ★青山ゆみこさん(ライター) 「「自分の声を聞く」ってむずかしい。でも「自分の身体を感じる」ことはできるかもしれない。それは自分を慈しむってこと。」 *** この本が目指すのは、「自分のダメなところを変える」ことではありません。 あなたが負った傷を、そっと癒すためのセルフケアです。 そのために必要なのは、自分の話を、正しいとか間違ってるとかジャッジせずに、ぜんぶ聞くこと。 そして、勇気を出してぜんぶ語ること。 【著者紹介】 尹 雄大(ゆん・うんで) 1970年、神戸市生まれ、テレビ制作会社勤務を経てライターになる。 主な著書に『さよなら、男社会』『つながり過ぎないでいい』(以上、亜紀書房)、『句点。に気をつけろ』(光文社)、『聞くこと、話すこと』(大和書房)など。 武術や整体を通して得た経験から身体と言葉の関わりに興味を持っており、その一環としてインタビューセッションを行っている。 公式サイト:https://nonsavoir.com/ (亜紀書房)
-

『境界線を曖昧にする ケアとコミュニティの関係を耕す』糟谷 明範
¥2,420
--- 《一人ひとりが望む健康な暮らしを実現するには、「医療・福祉」と「人」と「まち」のあいだにどんな「つながり」が必要なのだろうか――。「医療・福祉の専門職」と「まちの一住民」という二つの視点を往復し、人と人との「つながり」のかたちを模索しながら訪問看護ステーションやコミュニティカフェを運営してきた理学療法士の実践と思考の記録》 【本書より】 僕たち医療や福祉の専門職の多くは、「目の前に困ってる人がいるなら、すぐに解決してあげなきゃ」と思う癖がついてるし、たくさんの「科学的に正しい選択肢」を持っている。でも、それってあくまでも医療というフィールドでの正しさであって、その人の人生の中での正しさとは限らない。だからこそ、「ゆらぎ」の視点が大事になる。そして「ゆとり」を持って関われることが、相手にとっての、その瞬間における答えを一緒に見つけていく上で欠かせないんだと思う。(第5章「弱く、淡く、ゆるやかなつながりの確かさ」より) (ブルーブラックカンパニー)
-

『ユニヴァースのこども 性と生のあいだ』シリーズ「あいだで考える」
¥1,870
--- 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ 「あいだで考える」 正解のない問いを考え、多様な他者と生きる。 --- 『ユニヴァースのこども 性と生のあいだ』中井 敦子 / 森岡 素直 敦子さんと素直さんは、互いを大切なパートナーとして、敦子さんが出産した満生ちゃんと3人で暮らしている。素直さんの性は女性/男性のどちらにもとどまらず、3人の関係は〈母親/父親/こども〉の枠に収まらない。性のあり方、関係性のあり方を枠にはめず、名前をつけず、ゆらぎ変化していく全体として日々の生を生きようとしてきた2人が、出会いの頃から満生ちゃんの誕生、現在の暮らしまでの出来事と思いを語った「声のおたより」の記録。(装画:ひうち棚) [著]中井 敦子(ナカイ アツコ) 中井敦子(なかい・あつこ) 1982年京都府生まれ。そのひと自身から生まれる表現とことばに興味をもち、こどもアトリエ(薬師山美術研究所)を営む。本の装画・挿画家でもあり、主な仕事に『能力で人を分けなくなる日』(最首悟著、創元社)、『海女たち』(ホ・ヨンソン著、姜信子、趙倫子訳、新泉社)、雑誌『ちいさい・おおきい・よわい・つよい』(ジャパンマシニスト社)など。アレクサンダー・テクニークの教師としても活動している。 [著]森岡 素直(モリオカ モトナオ) 森岡素直(もりおか・もとなお) 1981年大阪府生まれ。3年間のひきこもり生活を経て、生きることとジェンダー、セクシュアリティの関係を大学などで探究。高齢者介護施設で働いたのち、現在は中井敦子とともにこどもアトリエの活動に専念。「ちいさな自由図書館灯トモス」の活動も行う。 (創元社)
-

『ヨイヨワネ あおむけ編』ヨシタケシンスケ
¥924
--- 人気絵本作家のスケッチ集。「ヨイヨワネ」とは「良い弱音」。ネガティブにみえる「弱音」も反転させれば元気が出る(かもしれない)? ヨシタケさんがライフワークとして描きつづけるアイデアスケッチのなかから、近年の作品を選んだスケッチ集。「ヨイヨワネ」とは「良い弱音」という意味です。ネガティブな言葉とみなされがちな「弱音」を反転させ、にやりと笑えてちょっと元気が出る(かもしれない)スケッチ集をつくりました。人生はにがいけれど、救いだってあるんです。「あおむけ編」は、魂が疲れ気味のあなたを励ましてくれる一冊です。 (筑摩書房)
-

『ヨイヨワネ うつぶせ編』ヨシタケシンスケ
¥924
--- 息を吸って、弱音をはいて――。 息を吸って、弱音をはいて――。人生はにがいけれど、救いだってあるんです。しんどさを受け容れ、自分と折り合いをつけるためのイラスト集。 絵本作家ヨシタケシンスケのスケッチは弱音であふれていました── 不安を言語化し、弱音をはくことは、本人にとって気持ちを健全に保つために良いのかもしれません。しかし、他人の弱音はどうでしょう? おもしろいのか? 何かに貢献するのか? このスケッチ集で、壮大な実験があなたの手から始まろうとしています。「うつぶせ編」は、しんどさを受け容れ、自分と折り合いをつけるための一冊です。 (筑摩書房)
-

『言葉なんていらない? 私と世界のあいだ』シリーズ「あいだで考える」
¥1,760
--- 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ 「あいだで考える」 正解のない問いを考え、多様な他者と生きる。 --- 『言葉なんていらない? 私と世界のあいだ』古田 徹也 私たちは言葉を通して世界やそこに住む人々とかかわり、ともに暮らしている。でも、言葉による表現はときに不正確で、誤解やトラブルの元にもなる。はたして言葉は私と人々/世界をつなぐ「メディア」なのか、はたまた両者を隔てる「バリア」なのか。そもそも私たちは、「発話=言葉を発すること」によっていったい何をしているのか?――本書はこれらの問いから出発し、哲学的な視点を携えて、言葉を旅していく。SNSをはじめ、言葉に振り回されがちな日常の中で、言葉と親しくなり、より自由につきあっていくための一冊。(装画:土屋萌児) [著]古田 徹也(フルタ テツヤ) 古田徹也(ふるた・てつや) 1979年熊本県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科准教授。主に西洋近現代の哲学・倫理学を研究。著書に『謝罪論』(柏書房)『このゲームにはゴールがない』(筑摩書房)『いつもの言葉を哲学する』(朝日新書)『はじめてのウィトゲンシュタイン』(NHK BOOKS)『不道徳的倫理学講義』(ちくま新書)ほか。『言葉の魂の哲学』(講談社選書メチエ)で第41回サントリー学芸賞受賞。 (創元社)
-

『新百姓』002号
¥3,150
ーなぜ人類はいまだに毎日を遊んで暮らすことができないのか? 現代の社会システムに問いを投げかける雑誌『新百姓』。 第2号のテーマは偶然にも今年不足して話題となった「米をくう」。 --- 便利で安定した現在の米供給システムは、ありがたいもの。 しかし、効率のみを重視するあまり、稲作から炊飯まで、「米をくう」営みの中に溢れていた つくる喜びや楽しみも、失われてきたのではないでしょうか? 安定した米供給システムを土台にするからこそ、安心して、思いっきり「米をくう」で遊ぶ。 そんな新しい社会は、どうやったら実現できるのか? そんな想いのもと、本号では、 『まぁまぁマガジン』編集長で文筆家の服部みれいさん、 『米の日本史』などで知られる稲作文化研究の第一人者・佐藤洋一郎さん、 『小さな田んぼでイネづくり』などの著者で、石垣島で稲作に取り組む笹村出さんをはじめ、 常識に囚われずに、文明、テクノロジー、文化、技と知恵の各視点から、 「米をくう」を探究してきた先輩方との対話を通じて、新しいものの見方、最先端の問い、創造の余白に触れて参りました。 読めば、お米を釜で焚いてみたくなる。 読めば、自分で田んぼをやってみたくなる。 読めば、炊きたてのご飯がいつもの何倍も愛おしくなる。 そんな一冊になっていると思います。 --- (発行元の紹介文より) 米にちなみ、限定8888冊のみの流通。すべての裏表紙にシリアルナンバーが刻印されています。
-

『隣の国の人々と出会う 韓国語と日本語のあいだ』シリーズ「あいだで考える」
¥1,540
--- 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ 「あいだで考える」 正解のない問いを考え、多様な他者と生きる。 --- 『隣の国の人々と出会う 韓国語と日本語のあいだ』斎藤 真理子 いま、韓国の文学、音楽、ドラマや映画に惹かれ、その社会や言語に関心を持つ人はますます増えている。本書では、著者が韓国語(朝鮮語)を学び始めた背景、この言語の魅力、痛みの連続である現代史と文学の役割、在日コリアンと言語のかかわりなどを、文学翻訳の豊かな経験から親しみやすく語る。文字、音、声、翻訳、沈黙など、多様な観点から言葉の表れを捉え、朝鮮半島と日本の人々のあいだを考える1冊。(装画:小林紗織) [著]斎藤 真理子(サイトウ マリコ) 1960年新潟県生まれ。韓国文学の翻訳者。著書に『本の栞にぶら下がる』(岩波書店)『曇る眼鏡を拭きながら』(くぼたのぞみとの共著、集英社)『韓国文学の中心にあるもの』(イースト・プレス)、訳書にハン・ガン『別れを告げない』(白水社)チョ・ナムジュ『82年生まれ、キム・ジヨン』(筑摩書房)チョ・セヒ『こびとが打ち上げた小さなボール』(河出書房新社)パク・ミンギュ『カステラ』(共訳、クレイン)ほか多数。 (創元社)
-

『ホームレスでいること 見えるものと見えないもののあいだ』シリーズ「あいだで考える」
¥1,540
--- 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ 「あいだで考える」 正解のない問いを考え、多様な他者と生きる。 --- 『ホームレスでいること 見えるものと見えないもののあいだ』いちむら みさこ 著者は公園のテントに20年以上暮らし、ほかのホームレスたちと共に生きる場をつくりながら、ジェントリフィケーションやフェミニズム、貧困などをめぐる活動をしてきた。本書では、公園や路上での生活や、ほかのホームレス女性たちとの営み、街の再開発とそれに伴うホームレスの追い出し、ホームレスへの襲撃などを伝え、現代社会の風景の中の「見えているのに見えないことにされているもの」「隠されているもの」「消されたもの」について、読者に語りかける。(装画:いちむらみさこ) [著]いちむら みさこ(イチムラ ミサコ) 2003年から東京都内の公園のブルーテント村に住み、仲間と共に物々交換カフェ「エノアール」を、また、ホームレス女性のグループ「ノラ」を開く。国内外でジェントリフィケーションやフェミニズム、貧困などをめぐる活動をしている。著書に『Dearキクチさん、ブルーテント村とチョコレート』(キョートット出版)、責任編集書に『エトセトラ VOL.7 くぐりぬけて見つけた場所』(エトセトラブックス)がある。『小山さんノート』(エトセトラブックス)編者の「小山さんノートワークショップ」メンバー。 (創元社)
-

『生きのびるための事務』坂口恭平 原作/道草晴子 画
¥1,760
--- 芸術家でも誰でも、事務作業を疎かにしては 何も成し遂げられない。 夢を現実にするたった一つの技術、 それが《事務》です。 この作品は作家、建築家、画家、音楽家、 「いのっちの電話」相談員として活動する 坂口恭平が若い頃に出会った優秀な事務員・ ジムとの対話で学び、人生で実践した方法を 記したテキストを原作にコミカライズして、 《事務》ってめちゃくちゃ大事! ってことが漫画でわかる本です。 「自分に自信がない」 「ハードルを高く設定しがち」 「悩んで行動に移せない」 足らないことは《事務》でした。 【目次】 はじめに ジムとの出会い 第1講 事務は『量』を整える 第2講 現実をノートに描く 第3講 未来の現実をノートに描く 第4講 事務の世界には失敗がありません 第5講 毎日楽しく続けられる事務的『やり方』を見つける 第6講 事務は『やり方』を考えて実践するためにある 第7講 事務とは好きとは何か?を考える装置でもある 第8講 事務を継続するための技術 第9講 事務とは自分の行動を言葉や数字に置き換えること 第10講 やりたいことを即決で実行するために事務がある 第11講 どうせ最後は上手くいく あとがき (マガジンハウス)
-

『生 = 創 × 稼 × 暮』(イキル ハ ツクル カケル カセグ カケル クラス)
¥1,980
SOLD OUT
北海道森町を拠点とする「かくれんぼパブリッシング」の記念すべき1冊目の書籍。 あんこや、書店店主、薪ストーブ職人など、さまざまな形で創作活動を行う19名の「創作・生計・暮らしのバランス」が綴られています。 道は一つではなく、どんな道を選んでも悩み迷いながら進んでいくのだということ。 人生の岐路に立つ人を勇気づけてくれる本です。
-

『ハマれないまま、生きてます こどもとおとなのあいだ』シリーズ「あいだで考える」
¥1,760
--- 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ 「あいだで考える」 正解のない問いを考え、多様な他者と生きる。 --- 『ハマれないまま、生きてます こどもとおとなのあいだ』栗田 隆子 「『大人になる』ってどういうこと?」「私、何歳になっても『大人になった』気がしない」──いま、子どもと大人の境界はますます曖昧になっている。本書では、子どもにも大人にもハマれないまま生きてきた著者が、自らの内なる「子どもと大人のあいだ」を見つめ、そこにうごめく性と暴力、死への衝動や生きることへのあがきを正直に、時に飄々と描く。そして幼少時から周囲の求める「○○らしさ」と闘い、やがてフェミニズムとキリスト教に出会い、言葉と思想を獲得してきたプロセスを語りだす。子ども/大人の二分法を超えて、「ひと」のありようを問う1冊。(装画・ミロコマチコ) [著]栗田 隆子(クリタ リュウコ) 栗田隆子(くりた・りゅうこ) 1973年神奈川県生まれ。文筆家。大阪大学大学院で哲学を学び、シモーヌ・ヴェイユを研究。その後、非正規労働者として働きながら女性の貧困や労働問題の解決に向けたアクションを行うグループやネットワークにかかわる。現在は新聞・雑誌などでの執筆を中心に活動。著書に『呻きから始まる 祈りと行動に関する24の手紙』(新教出版社)、『ぼそぼそ声のフェミニズム』(作品社)、共著に『高学歴女子の貧困 女子は学歴で「幸せ」になれるか?』(光文社新書)など。 <訂正のお知らせ> 2024年5月刊行の『ハマれないまま、生きてます こどもとおとなのあいだ』(栗田隆子[著])に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。 訂正内容につきましては、下記をご参照ください。 【38ページ15行目~39ページ1行目】 (誤)あるいは私が子どもの頃は、親はもとより教師からの体罰もあたりまえだったが、2020年以降、体罰は法律で禁止されている。 ↓ (正)あるいは私が子どもの頃は親はもとより教師からの体罰は当然で、法律で禁止されるような行為ではないと思いこまされていた。 ※p.38~39の上記の記述について、学校における教師による体罰は、明治時代の教育令や小学校令ですでに禁止されていました。また、現行法である学校教育法11条でも、体罰は禁止されています。元の文章では、教師の体罰も2020年以降に禁止されたように読めてしまうため、「あるいは私が子どもの頃は親はもとより教師からの体罰は当然で、法律で禁止されるような行為ではないと思いこまされていた。」と著者より訂正をいたします。 (創元社)
-

『新百姓宣言』
¥1,100
SOLD OUT
なぜ人は生まれてきたのか? この問いに、わたしたちは、「つくる」を楽しむため、と応えます。 (冒頭・新百姓宣言より) 雑誌『新百姓』のエッセンスをまとめた1冊。 『新百姓』への導入として、また、さらに思考を深める手助けとしても。 --- 本書は、雑誌『新百姓』編集長が、『新百姓』の背景にある考えと経験、 そして『新百姓』に至るまでの試行錯誤のプロセスについて書いた本です。 人間がシステムに隷属するのではなく、創造の主体として、 一人ひとりの創造性がより自由に解放されるには? 本書では、今のCapitalism(資本主義)に至る社会システムのコンテキストとその本質や機能不全について考えた上で、 「つくる喜び」を最も大切にするCreativitism(創造性主義)というあり方を提示し、 それに向けた世界観や価値の転回について論じます。 そして、Creativitismの観点から見た暮らしや仕事のあり方と、 それに基づいた新たな社会の仕組みについて、仮説を提示します。 カネを最重視するCapitalismをはじめ、従来の権威的な主義と違って、 Creativitismが最も大切にする「つくる喜び」は、あくまで私たち一人ひとりが個人的に、 自らの感覚によってしか確認できないものです。 だからこそ、身の周りの衣食住から、物事の解釈や意味づけという「見方」まで、 あらゆるレイヤーで私たちは一人ひとりが創造の主体であり、 日常の中のどんな営みからでも、「つくる」を楽しみはじめられる。 Capitalismの限界が様々な面であらわになりつつある今、 既存の社会システムに疑問を持ち、生き方や働き方を根本的に考え直す人が増えているのではないでしょうか。 「常識」や「正解」にただ沿うのではなく、自分が本当に大切にしたいことを、大切にしたい。 狭い範囲でコントロールするのではなく、より広い縁起の中で、偶発性を楽しみつつ、 自分が思い描くものを、自らの手でつくってみたい。 もしもそういった思いを抱いているのならば、本書はそういう方々に友人のように寄り添い、問いかけ、背中を押し、 ともに考え歩むような一冊になり得ると思います。 また本書は、雑誌『新百姓』をさらに深く楽しんでいただけるようになる一冊でもあります。 本書が、手に取ってくださったお一人お一人にとって、 自身の秘めた創造性に気づき、より花開かせるきっかけの一つになれれば幸いです。 (ている舎)
-

『能力で人を分けなくなる日 いのちと価値のあいだ』シリーズ「あいだで考える」
¥1,540
--- 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ 「あいだで考える」 正解のない問いを考え、多様な他者と生きる。 --- 『能力で人を分けなくなる日 いのちと価値のあいだ』最首 悟 本書は、著者の第4子で重度の知的障害者である星子さんとの暮らしや、津久井やまゆり園事件の犯人「植松青年」との手紙のやりとり、また1977年から通い続けた水俣の地と水俣病などについて、10代の3人の若者を相手に語った記録である。能力主義と優生思想、人とのかかわり、個・自立・責任、差別、脳死、人の生死といのち……などをめぐって話しあい、いのちに価値づけはできるのか、「共に生きる」とはどういうことかを考える。(装画:中井敦子) [著]最首 悟(サイシュ サトル) 最首悟(さいしゅ・さとる) 1936年福島県生まれ。生物学者、社会学者、思想家。東京大学教養学部助手を27年間務め、1977年より第一次不知火海総合学術調査団(水俣病に関する実地調査研究)に参加、第二次調査団長を務めた。また障害者の地域作業所「カプカプ」の設立・運営に携わる。現在、和光大学名誉教授。著書に『いのちの言の葉』(春秋社)『新・明日もまた今日のごとく』(くんぷる)『「痞」という病いからの』(どうぶつ社)『星子が居る』(世織書房)ほか多数。 (創元社)
-

『アイヌもやもや 見えない化されている「わたしたち」と、そこにふれてはいけない気がしてしまう「わたしたち」の。』
¥1,760
--- ー漫画『ゴールデンカムイ』の監修にも参加!北原モコットゥナシがアイヌをとりまくもやもやを 丁寧に解説 日本の民族的マイノリティであるアイヌ。北海道が舞台のドラマでもその姿を目にすることはめったになく、教科書に載っているのも民族衣装を着た姿ばかり。非アイヌにとって、今を生きるアイヌの姿は、まるで厚い「もや」の向こう側にあるかのようです。アイヌは、どんなことに「もやもや」を感じているのか? その「もやもや」はどこから来るのか? 無知・無理解や差別の構造、そしてマイノリティとマジョリティの関係など、北原モコットゥナシが様々な視点から考察してゆきます。 ーアイヌが感じている「もやもや」を、田房永子が漫画で表現! 母からの過干渉への葛藤や男性を中心に回る社会への疎外感を、鋭い視点でユーモアをもって描いてきた田房永子。本書では、アイヌが日常のなかで出会うさまざまな「もやもや」を田房氏の手によって漫画化しています。マジョリティに優位な社会の仕組みや、まわりからの無理解により、まるで虚を衝かれたような感覚に陥る瞬間など、漫画を通して感覚的に共有することができます。 (303BOOKS)
-

『根っからの悪人っているの? 被害と加害のあいだ』シリーズ「あいだで考える」
¥1,760
--- 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ 「あいだで考える」 正解のない問いを考え、多様な他者と生きる。 --- 『根っからの悪人っているの? 被害と加害のあいだ』坂上香 著者の映画作品『プリズン・サークル』は、日本で1か所だけ、刑務所の中で行われている「TC(回復共同体)」という対話による更生プログラムを、20 代の受刑者4 人を中心に2 年間記録したドキュメンタリー。本書は、この映画を手がかりに、著者と10 代の若者たちが「サークル(円座になって自らを語りあう対話)」を行った記録である。映画に登場する元受刑者の2 人や、犯罪被害の当事者をゲストに迎え、「被害と加害のあいだ」をテーマに語りあう。(装画:丹野杏香) ◆ 坂上香(さかがみ・かおり) 1965年大阪府生まれ。ドキュメンタリー映画作家。NPO法人out of frame代表。一橋大学大学院社会学研究科客員准教授。映画作品に『Lifers ライファーズ 終身刑を超えて』『トークバック 沈黙を破る女たち』『プリズン・サークル』(文化庁映画賞・文化記録映画大賞受賞)、著書に『プリズン・サークル』(岩波書店)などがある。 (創元社)
-

『風をとおすレッスン 人と人のあいだ』シリーズ「あいだで考える」
¥1,540
--- 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ 「あいだで考える」 正解のない問いを考え、多様な他者と生きる。 --- 『風をとおすレッスン 人と人のあいだ』田中真知 中東やアフリカで長年過ごしてきた著者が、旅の経験や、古今東西のさまざまな文化や文学作品などの例をとおして、人と人との「あいだ」、また自分自身の中の「あいだ」を見つめ、そこに風をとおし、互いに自由になれる関係をつむぐ道を考える。迷いや悩みの多い10代やすべての方たちにとって、「私」も他者も大切に、軽やかに生きていくレッスンとなる一冊。(装画:nakaban) ◆ 田中真知(たなか・まち)1960年東京都生まれ。作家、あひる商会CEO、立教大学観光研究所研究員、元立教大学講師。エジプトに8年にわたって滞在し、中東・アフリカを旅して回るなかで、コミュニケーションや対話について考えるようになり、あひる商会を設立。著書に『旅立つには最高の日』(三省堂)『美しいをさがす旅にでよう』(白水社)『孤独な鳥はやさしくうたう』(旅行人)『増補 へんな毒 すごい毒』(ちくま文庫)ほか多数。『たまたまザイール、またコンゴ』(偕成社)で第1回斎藤茂太賞特別賞を受賞。 (創元社)
-
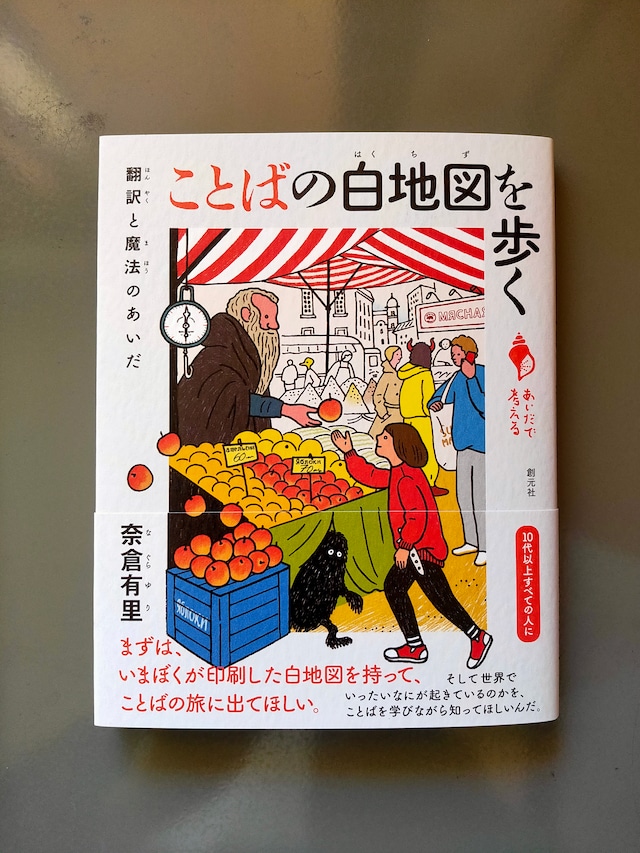
『ことばの白地図を歩く 翻訳と魔法のあいだ』シリーズ「あいだで考える」
¥1,540
--- 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ 「あいだで考える」 正解のない問いを考え、多様な他者と生きる。 --- 『ことばの白地図を歩く 翻訳と魔法のあいだ』奈倉有里 ロシア文学の研究者であり翻訳者である著者が、自身の留学体験や文芸翻訳の実例をふまえながら、他言語に身をゆだねる魅力や迷いや醍醐味について語り届ける。「異文化」の概念を解きほぐしながら、読書体験という魔法を翻訳することの奥深さを、読者と一緒に“クエスト方式”で考える。読書の溢れんばかりの喜びに満ちた一冊。(装画:小林マキ) ◆ 奈倉有里(なぐら・ゆり) 1982年東京都生まれ。ロシア文学研究者、翻訳者。ロシア国立ゴーリキー文学大学を日本人として初めて卒業。著書『夕暮れに夜明けの歌を』(イースト・プレス)で第32回紫式部文学賞受賞、『アレクサンドル・ブローク 詩学と生涯』(未知谷)などで第44回サントリー学芸賞受賞。訳書に『亜鉛の少年たち』(スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著、岩波書店、日本翻訳家協会賞・翻訳特別賞受賞)『赤い十字』(サーシャ・フィリペンコ著、集英社)ほか多数。 (創元社)
-

『SNSの哲学 リアルとオンラインのあいだ』シリーズ「あいだで考える」
¥1,540
--- 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ 「あいだで考える」 正解のない問いを考え、多様な他者と生きる。 --- 『SNSの哲学 リアルとオンラインのあいだ』戸谷洋志 あなたに考えてほしいのは、 「SNSをどう使うべきか」といったマニュアル的なことではなく SNSを使っているあなた自身が何者なのかという問いなのです。 承認・時間・言葉・偶然・連帯。 SNSを使う私たちを描く 新しい哲学の本。 10代の生活にすっかり溶け込んでいるSNSの利用をめぐるさまざまな現象――「ファボ」「黒歴史」「#MeToo運動」など――を哲学の視点から捉え直し、この世界と自分自身への新しい視点を提供する。若い読者に「物事を哲学によって考える」ことの面白さと大切さを実 践的に示す一冊。(装画:モノ・ホーミー) ◆ 戸谷洋志(とや・ひろし) 1988年東京都生まれ。関西外国語大学英語国際学部准教授。専攻は哲学・倫理学。技術思想および未来倫理学を探究する傍ら、「哲学カフェ」の実践などを通じて、社会に開かれた対話の場を提案している。著書に『スマートな悪』(講談社)『ハンス・ヨナスの哲学』(角川ソフィア文庫)ほか多数。 (創元社)
-

『自分疲れ ココロとカラダのあいだ』シリーズ「あいだで考える」
¥1,540
--- 10代以上すべての人のための人文書のシリーズ 「あいだで考える」 正解のない問いを考え、多様な他者と生きる。 --- 『自分疲れ――ココロとカラダのあいだ』頭木 弘樹 自分を好きとか嫌いとかに関係なく、 「自分がしっくりこない」「自分でいることになじめない」 というような違和感を覚えたことはないだろうか? なぜ、自分に疲れてしまうのか。 「自分」とは何なのか? 難病のカラダを持つ著者の ココロとカラダの探究ガイド。 難病の実体験に基づいたユニークな文学紹介活動を展開している著者が、「自分自身でいることに疲れを感じる」「自分自身なのになぜかなじめない」といった「違和感」を出発点にして、文学や漫画、映画など多彩なジャンルの作品を取り上げながら、心と体の関係性について考察していく。読者が「私だけの心と体」への理解を深める一助となる一冊。(装画:香山哲) ◆ 頭木弘樹(かしらぎ・ひろき) 文学紹介者。20歳のときに難病(潰瘍性大腸炎)にかかり、13年間の闘病生活を送る。そのときにカフカの言葉が救いになった経験から『絶望名人カフカの人生論』(飛鳥新社/新潮文庫)を編訳。著書に『食べることと出すこと』(医学書院)『ひきこもり図書館』(毎日新聞出版)ほか多数。 (創元社)
-

キム・ジヘ『差別はたいてい悪意のない人がする』
¥1,760
北山あさひ『ヒューマン・ライツ』刊行記念選書フェア「心に火を灯す13冊」 「悪意なき差別主義者」にならないために。自分の無知や無自覚と向き合うのは辛い けれど、その先にしか「差別のない社会」はないんですよね。 (北山あさひ・コメント) --- あらゆる差別は、マジョリティには「見えない」。 日常の中にありふれた排除の芽に気づき、真の多様性と平等を考える思索エッセイ。 韓国で16万部突破のベストセラー! (大月書店)
-

『写訳 春と修羅』
¥1,760
--- 詩:宮沢賢治 写真とエッセイ:齋藤陽道 /解説 若松英輔 「写訳」とされているように齋藤の写真は、 賢治の詩を「画」に翻訳する。 解説しているのではない。だが、齋藤の写真は、 私たちを賢治が感じていた世界に連れて行ってくれる。 ―巻末解説「言葉を写す詩人たち」(批評家・若松英輔)より NHKEテレ「ハートネットTV」で取り上げられるなど、 注目の写真家、齋藤陽道による3冊目の著作は、 詩人・宮沢賢治の詩を写真で翻案した、 これまでにない奇妙で美しい作品集。 彼方の世界の音律を紡いだ 詩人・宮沢賢治の4篇の詩、 「序」「春と修羅」「告別」「眼にて云ふ」。 音の無い世界を生きる写真家・齋藤陽道が、 東北を中心に撮影した78枚の写真群。 言葉の奥に流れている 無限の声に耳をすます、一冊。 〔プロフィール〕 齋藤陽道(さいとう・はるみち) 1983年東京都生まれ。写真家。都立石神井ろう学校卒業。陽ノ道として障害者プロレス団体「ドッグレッグス」所属。 2010年写真新世紀優秀賞(佐内正史選)。2013年ワタリウム美術館にて新鋭写真家として異例の大型個展を開催。近年はMr.Children やクラムボンといったミュージシャン、俳優・窪田正孝との作品など注目を集める。 写真集に『感動』(赤々舎)、『宝箱』(ぴあ)、宮沢賢治の詩を写真で翻訳した『写訳 春と修羅』(小社)がある。 2017年、7年にわたる写真プロジェクト「神話(一年目)」を発表。 (ナナロク社)
-

『パンでわかる包括的性教育 入学前までにやっておきたい!将来のための30のこと』
¥1,430
世界で一番やさしい性教育本!(帯文より) 「性教育」と聞くとドキドキ、ドギマギしてしまう人も少なくないかもしれませんが、 本書には大人が頭に思い浮かべるような「性表現」はほぼありません。 しかも、人ではなく「パン」を使って表現しているので安心して開くことができ、 ニシワキタダシさんの可愛くユーモアのある挿絵にクスッと微笑みながら、 「包括的性教育」「多様性」「子どもとの関わり方」について知ることができます。 「入学前までにやっておきたい!」というサブタイトルの通り、 未就学児のお子さんや、これから子どもが生まれるという方に特におすすめです。 小学生のお子さんをお持ちの方でも、まず初めの一冊としては参考になると思います。 --- 子どもを守るために、まずはおとなが知る! 「子どもの行動範囲が広がってきて成長を感じる一方、心配…」 「性教育に対してどうしても抵抗がある...」 「気にはなっているけど、何から始めたらいいかわからない…」 そんなママ・パパ必読! いま世界で学ばれている「包括的性教育」は、 多様性や人権を軸に、自分や相手を大切にすることからスタートします。 子どもが幼い頃から自分で自分の身を守り、 自分らしくハッピーに生きていくために、親が日常でできることとは? ユネスコ「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」の翻訳者である浅井春夫先生監修のもと、 性教育のイメージががらりと変わる新しい視点で、 おさえておきたい最初の30項目をお伝えします。 ●子どもが「自分のからだは自分だけのからだ」と知るために →3歳頃から自分のからだを自分で洗う習慣をつける ●子どもが嫌なことに対し「NO!」と言えるようになるために →親子で日頃から快・不快の気持ちを言葉にして伝え合う ●子どもが「性別に関わらずみんな平等」と知るために →親がジェンダーに縛られず、選択の自由を子どもに与える など (出版社紹介ページより)
-

『新百姓』001号
¥3,150
SOLD OUT
ーなぜ人類はいまだに毎日を遊んで暮らすことができないのか? <『新百姓』とは?> システムに封じられた人間の創造性の解放を促す雑誌です。効率や規模の拡大を最優先に追求する経済のあり方、人間一人ひとりがそれに従順であるように求められる巨大な社会システム。そういったものに疑問を持ち、新しい生き方を探究している人たちの問いと実践の物語を編み込んでお届けします。 6,966冊限定で”発酵”され、すべての裏表紙にシリアルナンバーが刻印されています。
書肆侃侃房「新鋭短歌シリーズ」一挙アップ!