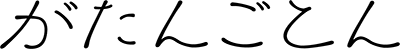-

稲葉京子『ガラスの檻』
¥734
--- 初期の稲葉作品は、一見、伝統的な近代のリアリズムを継承しているように見えるが、その実、どの歌もさりげなく仮構がほどこされている。それは、修辞という意味合いではなく「大切なものは目に見えない」という悲哀と、「自分にだけ見えてしまう」畏怖の念であろう。(菊池裕「解説」より) いつの日か倖せを山と積みてくる幻の馬車は馭者のない馬車 いとしめば人形作りが魂を入れざりし春のひなを買ひ来ぬ 君もまた知りてゐるべき静けさの中にして吾に満ちて来し毒 (現代短歌社・第一歌集文庫)
-

鵜飼康東『断片』
¥734
(現代短歌社・第一歌集文庫)
-

田中子之吉『現身』
¥734
(現代短歌社・第一歌集文庫)
-

小高賢『耳の伝説』
¥734
(現代短歌社・第一歌集文庫)
-

大下一真『存在』
¥880
--- この歌集『存在』の一首一首はまるで、この世界から与えられた様々な公案に、若き禅僧が苦悶し、全身を奮い立たせて答えを出そうとする、そんな精神の表れにも見える。(略)そうした精神の未熟を見つめながら人は移ろっていくのではないか。少なくとも僕は、この歌集の潔癖さに言いようのない愛着を感じる。(黒瀬珂瀾「解説」より) 夏の陽を葉に遊ばせて一樹立つこの雄々しさにいたり難しも 若き死も枯木朽ちゆくごとき死も見て来ぬ闇に尿を放つ 穢土と呼ぶこの世の冬ぞ仰ぐとき無数の切片天より下る (現代短歌社・第一歌集文庫)
-

平山良明『あけもどろの島』
¥880
--- 解説 光森裕樹 蘇生の喜びもつかのま、二十数万の生霊の骨の埋れている島の上には、平和への悲願をせせら笑いつつ、巨大な基地が築かれた。平山君は、この島の「宿命と疎外」を歎きつつしかも「太陽の魂」を失わない。 仲宗根政善 今日の沖縄の問題を、私達はまだほんとうに現地に生活している人たちと同じ感情、感覚で把握していない。理解しているつもりでいるのが一層よくないのだ。ほんとうの悲しみや、いかりは、底の深いところに沈んでいるのだ。 中野菊夫 (現代短歌社・第一歌集文庫)
-

安田純生『蛙声抄』
¥880
--- 解説 門脇篤史 歌壇における文語の第一人者たる著者が39歳の時、 口語短歌の激流に抗うように上梓した第一歌集。 投げうたれ砕けむさまを思ひつつ古道具屋に購ふ青磁 昼顔の花のかたへに瑠璃いろの翅とぢがたき死際の蝶 団子虫ゆびを触るれば背をまろむ はかなきわざに過す夕ぐれ たはむれに殺めし蛙も共に鳴き寝ねがたき夜の耳をうしはく (現代短歌社・第一歌集文庫)
-

草柳繁一『胡麻よ、ひらけ』
¥880
--- 草柳の歌を読むと、短歌の自由さに触れ直したような気持ちになる。リズムの気持ちいい歌や、喩を通じてこころを詠う歌。他にも、妻や娘のことを素直に愛する歌などもある。(中略)一見まとまりがなくてばらばらなようにも見えるが、しかし何度も読んでいくと、どの歌も草柳らしい、自在な息づかいがあるように感じられてくるのである。(阿波野巧也「解説」より) 胡麻よひらけ胡麻よひらけといふ声の低き呪言(じゆごん)の今宵きこゆる 荘周が夢に胡蝶となりて飛ぶ眩ゆき春になりにけるかな これやこの心の交感(コレスポンダンス)或る夜閃き或る夜仄かに (現代短歌社・第一歌集文庫)
-
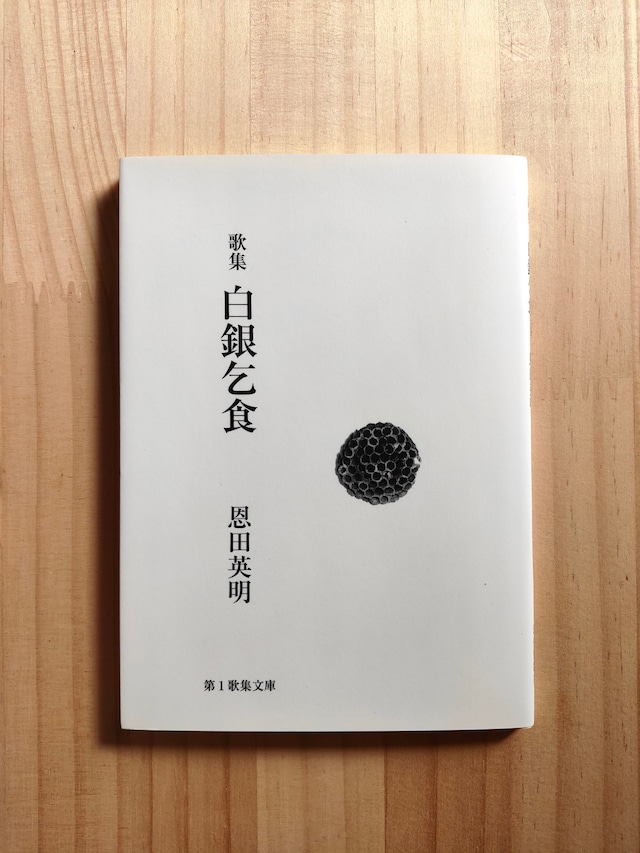
恩田英明『白銀乞食』
¥734
--- 今までは比較的安らかに作歌を続けてきたのだが、もう、そうはいかなくなるだろうという予感がするのだ。文学としての短歌の達成を欲するからには、あらゆる作家、作品に対峙せざるを得ないだろう。故に私はその出発の足掛りとして、この集を編んだのである。(恩田英明「あとがき」より) 吹く風の煽(あふ)るままにて馬酔木の花盛りなる樹の内部(なか)見ゆるまで 喉(のど)渇くわれは泉にはらばひてさびしき空の底を覗くも 口付けてなにか危ふし笑み割るる柘榴(せきりう)は種子こぼれむとして (現代短歌社・第一歌集文庫)
-
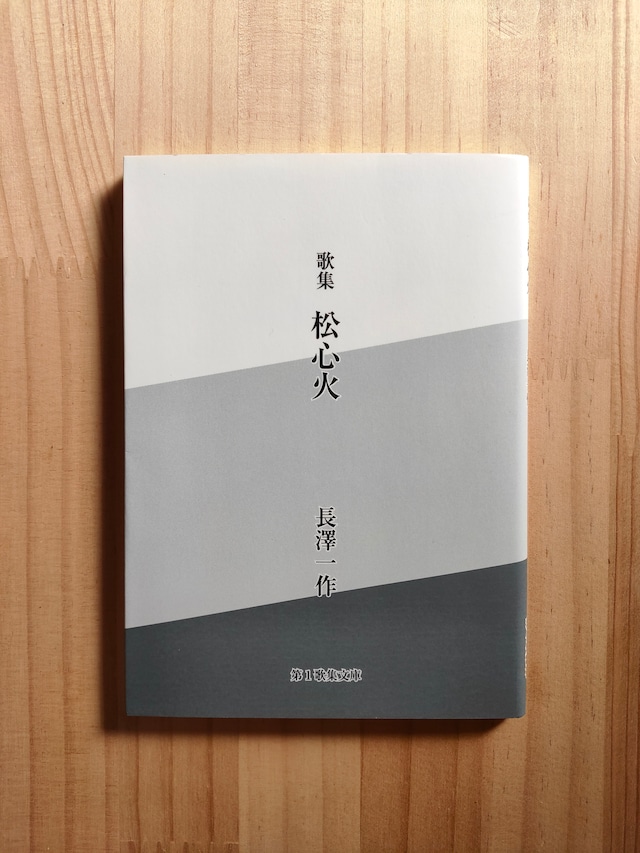
長澤一作『松心火』
¥734
(現代短歌社・第一歌集文庫)
-

松田さえこ『さるびあ街』
¥734
--- 『さるびあ街』は半世紀以上も前の歌集だが、今読んでも心に響く新鮮さを持っている。それはたぶん一首一首の言葉が、生きることに苦悩しつつも、ふたたび強く立ち上がろうとする凛とした意志をはらんでいるからだと思う。(大森静佳「解説」より) かく生きて吾に如何なる明日あらん厨の窓に夕雲動く まぶしきまで明るき部屋に吾の咽喉渇き別離を告げんとしたり 引く潮のまた忽ちに寄せてくる渚にしぶき浴びつつぞ佇つ (現代短歌社・第一歌集文庫)
-

大島史洋『藍を走るべし』
¥880
--- 実景や状況をそのまま言葉に定着させるのではなく、それを(過剰に)自身(の理想)に引き付けてべつのものに転換してしまうありよう、それが「観念」化ということではないかと思う。そのようにとらえたとき、『藍を走るべし』はいかにも観念に充ちている。そしてそれを促すエネルギーの源に「若さ」がある。(染野太朗「解説」より) ひそやかにひとりの苦悶の暮れゆけば雷とどろきて夜を走るべし いま僕におしえてほしいいちにんの力のおよぶ国のはんいを かぎろいの燃えたつなかに塔はたち 登れ君らにたおされるまで (現代短歌社・第一歌集文庫)
-

伊藤一彦『暝鳥記』
¥734
--- 『瞑鳥記』は私にとって血なまぐさく、それゆえ、ときに生への激しい希求を感じさせる歌集である。(大口玲子「解説」より) 水中のようにまなこは瞑りたりひかるまひるのあらわとなれば われらもつあるかなきかの自由よりゆたかなるかな 一滴の血 おとうとよ忘るるなかれ天翔ける鳥たちおもき内臓もつを (現代短歌社・第一歌集文庫)
書肆侃侃房「新鋭短歌シリーズ」一挙アップ!