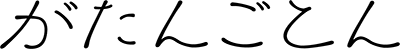-

『僕には鳥の言葉がわかる』鈴木俊貴
¥1,870
--- ◇書店員が選ぶノンフィクション大賞2025 ◇第24回新潮ドキュメント賞 ◇第13回河合隼雄学芸賞 爽快な読後感が大人気! ◎山極壽一さん(総合地球環境学研究所所長) 「現代のドリトル先生による新しい動物言語学の誕生だ」 ◎俵万智さん(歌人) 「面白すぎた!やるじゃないか、シジュウカラ。学問って、学ぶこと以上に問うことなのだ。熱い『言葉論』としてもオススメです」 ◎仲野徹さん(生命科学者) 「内容は深いが、文章は平易にしてユーモアたっぷり。これまで読んだサイエンス本でベスト」 ◎養老孟司さん(解剖学者) 「好きこそものの上手なれ、という。でも論語ではさらに上があるとする。これを好む者は、これを楽しむ者に如かず。楽しんでやっている人にはかなわない。著者の研究はまさに『これを楽しむ』の境地に入っている」 :::::::::::::::::::::::: 言葉を持つのは人間だけであり、鳥は感情で鳴いているとしか認識されていなかった「常識」を覆し、「シジュウカラが20以上の単語を組み合わせて文を作っている」ことを世界で初めて解明した研究者による科学エッセイ。 〈 編集者からのおすすめ情報 〉 本書の草稿を拝読したとき、何より感動したのは、鈴木先生が「シジュウカラのことが好きだ、もっと知りたい」というまっすぐな気持ちで、自然の中に身を置いて根気強く鳥たちをよく観察する姿勢でした。文系、理系、アウトドア派、インドア派問わず、何かを「好き」と思う気持ちを大事にすることで、日常生活の中でも新鮮な驚きや気づきが得られ、ひいては世界的な発見にまで繋がる--これは読者の皆さまにとっても、ポジティブなメッセージとなることと思います。 本文内のイラストもすべて鈴木先生自身によるもの! 細部までかわいらしく描かれているのは、愛と興味をもって丁寧に相手を観察する鈴木先生ならではのタッチです。 (小学館)
-

永井玲衣『さみしくてごめん』
¥1,760
--- ロングセラー『水中の哲学者たち』で颯爽とデビューした在野の若手哲学者・永井玲衣の最新エッセイ。世界の奥行きを確かめる。 「わたしはいつまでも驚いていたい。こわがっていたい。絶望して、希望を持ちたい。この世界から遊離せずに、それをしつづけたい。世界にはまだまだ奥行きがあるのだから。」 哲学は心細い。さみしい。だがわたしは、さみしいからこそ哲学をしているような気がする。生まれてきたことがさみしい。わからないことがさみしい。問いをもつことがさみしい。問いと共に生きることがさみしい。(本文より) ことばが馬鹿にされ、ことばが無視され、ことばが届かないと思わされているこの世界で、それでもことばを書く理由は何だろう。わたしの日記は、戦争がはじまって終わっている。あの瞬間から、日記は戦時中のものとなった。 だが、ほんとうにそうなのだろうか。戦争はずっとあったし、いまもある。わたしが絶望したあの戦争は、いまもつづいている。だからあの日記はすでに戦時中のものだったし、この本も、やはり戦時中のものである。 とはいえ、わたしたちの生活に先立って、戦争があるわけではない。生活の中に戦争が入り込むのだ。どうしたって消すことのできない、無数の生の断片があるのだ。たとえ「対話」ができず、あなたのことばを直接きくことができなかったとしても、決して「ない」のではない。(「あとがき」より) (大和書房)
-

『新百姓』002号
¥3,150
ーなぜ人類はいまだに毎日を遊んで暮らすことができないのか? 現代の社会システムに問いを投げかける雑誌『新百姓』。 第2号のテーマは偶然にも今年不足して話題となった「米をくう」。 --- 便利で安定した現在の米供給システムは、ありがたいもの。 しかし、効率のみを重視するあまり、稲作から炊飯まで、「米をくう」営みの中に溢れていた つくる喜びや楽しみも、失われてきたのではないでしょうか? 安定した米供給システムを土台にするからこそ、安心して、思いっきり「米をくう」で遊ぶ。 そんな新しい社会は、どうやったら実現できるのか? そんな想いのもと、本号では、 『まぁまぁマガジン』編集長で文筆家の服部みれいさん、 『米の日本史』などで知られる稲作文化研究の第一人者・佐藤洋一郎さん、 『小さな田んぼでイネづくり』などの著者で、石垣島で稲作に取り組む笹村出さんをはじめ、 常識に囚われずに、文明、テクノロジー、文化、技と知恵の各視点から、 「米をくう」を探究してきた先輩方との対話を通じて、新しいものの見方、最先端の問い、創造の余白に触れて参りました。 読めば、お米を釜で焚いてみたくなる。 読めば、自分で田んぼをやってみたくなる。 読めば、炊きたてのご飯がいつもの何倍も愛おしくなる。 そんな一冊になっていると思います。 --- (発行元の紹介文より) 米にちなみ、限定8888冊のみの流通。すべての裏表紙にシリアルナンバーが刻印されています。
-

西村玲子『ハチのいない蜂飼い』
¥1,980
--- 「この人を待っていた。」-養老孟司- 透明感のある文章に魂が洗われる日本版「センス・オブ・ワンダー」誕生! かつてレイチェル・カーソンが「沈黙の春」を予言した。2019年、ミツバチのいない養蜂家になった著者が、ニホンミツバチとの暮らしを軸に、自然と寄り添うべき暮らしの姿を自身を通して模索する。郷土の芸能、季節の営みなども織り交ぜた春夏秋冬をめぐる物語的エッセイ。小さな生きものたちとの暮らしを通じて得た「わたしは何も知らない」とは。 蜂をめぐる自然と郷土の暮らしの物語。 養老孟司氏との対談を収録。 <目次> ○ニホンミツバチの世界 ○春 厳しい越冬/希望と旅立ちの春/ニンホンミツバチが気に入る物件作りと分蜂/ノア ○夏 夏のミツバチ/夏の郡上/美しいワサビ田のお話/お米づくりと昆虫の暮らし/年に一度の採蜜/ミツバチの優れた集団防衛/天敵/ヘボ獲りの話/ニホンミツバチとの 出会い/それぞれの暮らし、生きる姿 ○秋・冬 台風/白鳥神社のお祭り/晩秋のコケ採り/冬のしろとり ○再び、春 ノアとの別れ/それでも春は来る ○セイヨウミツバチとニホンミツバチ ○バイオフィリア対談 養老孟司×西村玲子 自然の力を得て生きる ○養老先生へ
-

『中学生から知りたいパレスチナのこと』
¥1,980
--- この本から、始まる 新しい世界史=「生きるための世界史」 あらゆる人が戦争と自分を結びつけ、歴史に出会い直すために。 アラブ、ポーランド、ドイツを専門とする三人の対話から はじめて浮かび上がる「パレスチナ問題」。 世界史は書き直されなければならない。 *** 岡「今、必要としているのは、近代500年の歴史を通して形成された『歴史の地脈』によって、この現代世界を理解するための『グローバル・ヒストリー』です」 小山「西洋史研究者の自分はなぜ、ヨーロッパの問題であるパレスチナの問題を、研究領域の外にあるかのように感じてしまっていたのか」 藤原「力を振るってきた側ではなく、力を振るわれてきた側の目線から書かれた世界史が存在しなかったことが、強国の横暴を拡大させたひとつの要因であるならば、現状に対する人文学者の責任もとても重いのです」 *** (ミシマ社)
-

『私が諸島である カリブ海思想入門』
¥2,530
--- 「なぜハイデガーやラカンでなければならない? 僕たちにだって思想や理論はあるんだ」 カリブ海思想について新たな見取り図をえがく初の本格的な入門書。 西洋列強による植民地支配の結果、カリブ海の島々は英語圏、フランス語圏、スペイン語圏、オランダ語圏と複数の言語圏に分かれてしまった。それらの国々をそれぞれ孤立したものとしてではなく、諸島として見るということ。カリブ海をひとつの世界として認識し、その独自の思想を体系化する画期的著作。これからのカリブ海思想研究のためのリーディングリストを付す。 【著者プロフィール】 中村達(なかむら・とおる) 1987年生まれ。専門は英語圏を中心としたカリブ海文学・思想。西インド諸島大学モナキャンパス英文学科の博士課程に日本人として初めて在籍し、2020年PhD with High Commendation(Literatures in English)を取得。現在、千葉工業大学助教。 (書肆侃侃房)
-

『新百姓宣言』
¥1,100
SOLD OUT
なぜ人は生まれてきたのか? この問いに、わたしたちは、「つくる」を楽しむため、と応えます。 (冒頭・新百姓宣言より) 雑誌『新百姓』のエッセンスをまとめた1冊。 『新百姓』への導入として、また、さらに思考を深める手助けとしても。 --- 本書は、雑誌『新百姓』編集長が、『新百姓』の背景にある考えと経験、 そして『新百姓』に至るまでの試行錯誤のプロセスについて書いた本です。 人間がシステムに隷属するのではなく、創造の主体として、 一人ひとりの創造性がより自由に解放されるには? 本書では、今のCapitalism(資本主義)に至る社会システムのコンテキストとその本質や機能不全について考えた上で、 「つくる喜び」を最も大切にするCreativitism(創造性主義)というあり方を提示し、 それに向けた世界観や価値の転回について論じます。 そして、Creativitismの観点から見た暮らしや仕事のあり方と、 それに基づいた新たな社会の仕組みについて、仮説を提示します。 カネを最重視するCapitalismをはじめ、従来の権威的な主義と違って、 Creativitismが最も大切にする「つくる喜び」は、あくまで私たち一人ひとりが個人的に、 自らの感覚によってしか確認できないものです。 だからこそ、身の周りの衣食住から、物事の解釈や意味づけという「見方」まで、 あらゆるレイヤーで私たちは一人ひとりが創造の主体であり、 日常の中のどんな営みからでも、「つくる」を楽しみはじめられる。 Capitalismの限界が様々な面であらわになりつつある今、 既存の社会システムに疑問を持ち、生き方や働き方を根本的に考え直す人が増えているのではないでしょうか。 「常識」や「正解」にただ沿うのではなく、自分が本当に大切にしたいことを、大切にしたい。 狭い範囲でコントロールするのではなく、より広い縁起の中で、偶発性を楽しみつつ、 自分が思い描くものを、自らの手でつくってみたい。 もしもそういった思いを抱いているのならば、本書はそういう方々に友人のように寄り添い、問いかけ、背中を押し、 ともに考え歩むような一冊になり得ると思います。 また本書は、雑誌『新百姓』をさらに深く楽しんでいただけるようになる一冊でもあります。 本書が、手に取ってくださったお一人お一人にとって、 自身の秘めた創造性に気づき、より花開かせるきっかけの一つになれれば幸いです。 (ている舎)
-

朴沙羅『家(チベ)の歴史を書く』
¥990
北山あさひ『ヒューマン・ライツ』刊行記念選書フェア「心に火を灯す13冊」 韓国・済州島から日本へやってきた親族のオーラルヒストリー。「四・三事件」の体 験、日本での生活、差別、仕事。個人的であいまいなところにこそ本当の歴史がある と教えてくれる一冊です。 (北山あさひ・コメント) --- 「自分の親戚がどうやら「面白い」らしいことは知っていた」社会学者である著者は、済州島から日本へ来た親族にインタビューする。「社会学は過去をどのように扱えるのか」「ひとの語りを聞くとはどういうことか」自問しながら、著者は伯父二人と伯母二人の生活史を聞きとっていく。亡くなった伯父との約束を果たすべく書いてみせた、ある家(チベ)の歴史。 (筑摩書房)
-

瀬川拓郎『アイヌ学入門』
¥1,100
北山あさひ『ヒューマン・ライツ』刊行記念選書フェア「心に火を灯す13冊」 典型的な狩猟・採集の民としてではなく、荒海を越えて樺太や中国(元)にまで活動 範囲を広げていたアイヌの姿を追う、というのが本書。人に合わせて言葉や文化も移 動する、そのダイナミズムに魅了されます。 (北山あさひ・コメント) --- 海を渡り北方世界と日本を繋ぐ大交易民族としてのアイヌ。中国王朝と戦うアイヌ。従来のステレオタイプを覆し、ダイナミックに外の世界と繋がった「海のノマド」としてのアイヌ像を様々なトピックから提示する。 (講談社現代新書)
-

ブレイディみかこ『リスペクト ─R・E・S・P・E・C・T』
¥1,595
北山あさひ『ヒューマン・ライツ』刊行記念選書フェア「心に火を灯す13冊」 ロンドンのシェルターに身を寄せる、若きシングルマザーたちの尊厳のための戦い。 理不尽な社会で声を上げること、支え合うこと、人権とは何なのか。全部、他人事で はないのです。 (北山あさひ・コメント) --- 2014年にロンドンで実際に起きた占拠事件をモデルとした小説。ホームレス・シェルターに住んでいたシングルマザーたちが、地方自治体の予算削減のために退去を迫られる。人種や世代を超えて女性たちが連帯して立ち上がり、公営住宅を占拠。一方、日本の新聞社ロンドン支局記者の史奈子がふと占拠地を訪れ、元恋人でアナキストの幸太もロンドンに来て現地の人々とどんどん交流し…。「自分たちでやってやれ」という精神(DIY)と、相互扶助(助け合い)と、シスターフッドの物語。 (筑摩書房)
-

『新百姓』001号
¥3,150
SOLD OUT
ーなぜ人類はいまだに毎日を遊んで暮らすことができないのか? <『新百姓』とは?> システムに封じられた人間の創造性の解放を促す雑誌です。効率や規模の拡大を最優先に追求する経済のあり方、人間一人ひとりがそれに従順であるように求められる巨大な社会システム。そういったものに疑問を持ち、新しい生き方を探究している人たちの問いと実践の物語を編み込んでお届けします。 6,966冊限定で”発酵”され、すべての裏表紙にシリアルナンバーが刻印されています。
-

『ちきゅうパスポート』
¥1,980
子どもたちへ贈りたい「想像の国」が描かれた、希望ある未来へのパスポート。 あべ弘士さん、石川えりこさん、ささめやゆきさん、田島征三さんと、編集者らが発起人となり、24人の絵本作家が共作した蛇腹折りの小さな絵本が誕生しました。 --- いま同じ地球の上で、戦争に巻き込まれ、苦しんでいる子どもたちがいます。また、地球を覆うパンデミックも、なかなか収束しません。この閉塞感のある日常で、国境を越えてえて子どもたちに希望を伝えたいと、絵本作家たちによる「ちきゅうパスポート」という企画が動き出しました。 国境のない国々を想像力で自由に行き来でき、地球上のみんなが手と手を結びあえる、ジャバラ絵本の形を考えました。絵本作家には、1見開きずつ「想像の国」を考えていただき、次の国へとつながるような絵を描いていきました。 日本をはじめ6か国の24名の絵本作家が、子どもたちへのメッセージとして描いた作品がこの『ちきゅうパスポート』です。 ※本書の収益の一部は、ウクライナの子どもたちを支援する団体へ寄付されます。
-
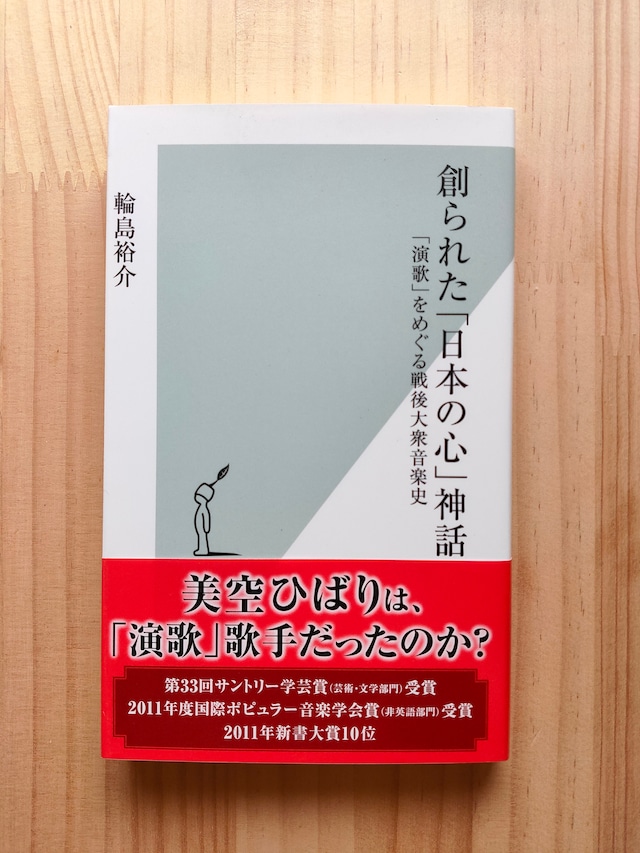
輪島裕介『創られた「日本の心」神話 「演歌」をめぐる戦後大衆音楽史』
¥1,045
\『寂しさでしか殺せない最強のうさぎ』発売記念・山田航オススメ本フェア/ <山田さんからのおすすめコメント> 「創られた伝統」という理論に則り、演歌というものが昭和期に「日本の伝統」として捏 造されていった過程を論じた本。文化に関わる人はみんな意識しておかなくてはならない 歴史。 --- 「演歌は日本の心」と聞いて、疑問に思う人は少ないだろう。落語や歌舞伎同様、近代化以前から受け継がれてきたものと認識されているかもしれない。ところが、それがたかだか四〇年程度の歴史しかない、ごく新しいものだとしたら? 本書では、明治の自由民権運動の中で現れ、昭和初期に衰退した「演歌」――当時は「歌による演説」を意味していた――が、一九六〇年後半に別な文脈で復興し、やがて「真正な日本の文化」とみなされるようになった過程と意味を、膨大な資料と具体例によって論じる。 いったい誰が、どういう目的で、「演歌」を創ったのか?
-

平田オリザ『演劇入門』
¥924
\『寂しさでしか殺せない最強のうさぎ』発売記念・山田航オススメ本フェア/ <山田さんからのおすすめコメント> 「現代口語演劇」の入門書。演劇は観ないという人ほど、読むと目から鱗が落ちると思う 。「日本語とは何か」ということを一番教えてくれた本。平田オリザと穂村弘が同い年な のすごいよね。 --- 若き天才が全て明かす「芝居作りの技術」。シェイクスピアはなぜ四世紀にわたって人気なのか? 日本で対話劇が成立しづらいのはなぜか? 戯曲の構造、演技・演出の方法を平易に解説する画期的演劇入門書!
-

【サイン本あり】齋藤 陽道『育児まんが日記 せかいはことば』
¥1,980
写真と文章でしか齋藤陽道さんを知らない人に、ぜひ手にとってみてほしいな。 日々、育児に励んでいる人にも。子どもたちにも。 絵の多いページは、小さい子どもと読んでも楽しめそうだな。 多様性、なんて言葉でいろんな問題をひっくるめて誤魔化すエライ大人にも届けたい。 「手話」を知りたい人はもちろん、「手話」を通して自分の知らない世界を広げたい人に。 そして、「生きること」にわくわくしたいすべての人に。 B5の大き目サイズです。 https://harumichi-saito.theletter.jp/posts/ab7fc390-d1aa-11ec-a542-ffcfc04b53ea こちらの下の方にある、齋藤陽道さんの熱いメッセージもぜひお読み下さい。 --- 写真家や文筆家としても活躍する齋藤陽道さんが描くまんが日記が、196ページのコミックエッセイになりました。 手話で話すろう者の両親と、耳の聴こえる0才3才のこどもたち(コーダ)の、「ことば」の成長と発見を描いています。 【プロフィール】 齋藤陽道(さいとう・はるみち) 1983年9月3日、東京都生まれ。O型。写真家。文筆家。マンガ家。好きな食べ物は、きくらげ。ちゃんぽん。 都立石神井ろう学校専攻科卒業。2020年から熊本在住。陽ノ道として障害者プロレス団体「ドッグレッグス」所属。 2010年、写真新世紀優秀賞(佐内正史選)。2013年、ワタリウム美術館にて異例の大型個展を開催。2014年、日本写真協会新人賞受賞。写真集『感動』『感動、』(赤々舎)、『宝箱』(ぴあ)、著書『写訳春と修羅』『それでも それでも それでも』(ナナロク社)、『声めぐり』(晶文社)『異なり記念日』(医学書院、第73回毎日出版文化賞企画部門受賞)などがある。 (出版社:ナナロク社)
-

齋藤陽道(写真)『日本国憲法』
¥1,100
SOLD OUT
日本国憲法は、国民を守ってくれているのか、それとも、縛っているのか。 いつ突きつけられるかわからない、憲法改正への判断。 他人事と割り切ってばかりいられない、違憲か合憲という審判。 かたく感じる文字の羅列も、齋藤陽道さんの写真と共に眺めると、 すーっと体の中に入ってくるような気がします。 いつでも手に取れるよう、本棚に一冊はどうぞ、日本国憲法を。 --- 日本国憲法は誰のものか? もう一度読み、感じ、考える私たち自身の憲法。 日本国憲法の条文全文に、写真家・齋藤陽道さんのカラー写真24点を組み合わせたハンディな一冊。 戦後70余年、私たちの幸福と平和の土台となってきた憲法を、いまの暮らしのなかでそれぞれの人生を生きる人々の姿を深くとらえた写真とともに読み直す。 ■著者 齋藤陽道(さいとう・はるみち) 1983年、東京都生まれ。写真家。都立石神井ろう学校卒業。2020年から熊本県在住。陽ノ道として障害者プロレス団体「ドッグレッグス」所属。2010年、写真新世紀優秀賞(佐内正史選)。2013年、ワタリウム美術館個展。2014年、日本写真協会新人賞受賞。 写真集に『感動』、続編の『感動、』(赤々舎)。著書に『写訳 春と修羅』(ナナロク社)、『異なり記念日』(医学書院・シリーズケアをひらく、第73回毎日出版文化賞企画部門受賞)、『声めぐり』(晶文社)がある。 (出版社:港の人)
-

『モン族の襟布』
¥2,310
SOLD OUT
中国南部、ベトナム、ラオス、タイの山岳地帯に暮らす少数民族、モン族。 多くの歴史の中で作られてきた美しく、素朴な手仕事。一針一針に刻まれた、重みや、祈りを感じられるような写真集です。
-

エトセトラ vol.1
¥1,100
フェミマガジン、エトセトラ 1号。特集「コンビニからエロ本がなくなる日」田房さんのエッセイや漫画で、すごく読んでい楽しい。評論めいたものより、エッセイや、回顧、純粋な疑問や葛藤など、色々な人の話を聞ける本。編集者など、業界の人の話も多い、貴重な記録だと思います。
書肆侃侃房「新鋭短歌シリーズ」一挙アップ!